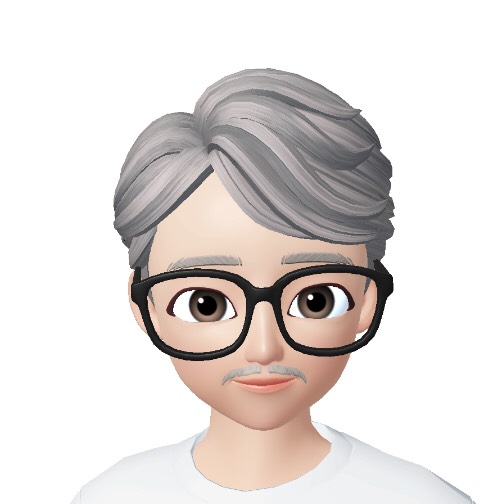
 | ザムスト zamst COOL SHADER (冷感ポンチョ) 389503 熱中症対策 UVカット 冷感 価格:4,499円 |
![]()
はじめに
この記事を書いていて息子の4種年代が懐かしいく思い出されます。
振返ると4種の時代は、6年間の成長が凝縮されていて思い出も詰まっています。
そして、この年代の子は無邪気さもあり、サポートのし甲斐がある世代です。
その中でも、4年生以降の悩みとして、移籍やジュニアユース世代に向けての進路選択は大きな出来事の一つとなることは間違いありません。
その中で、どのような選択をしても反省はつきもので、そこで起きた出来事は全て受け入れるしかありませんし、乗り越えていかなければなりません。
それが人生の醍醐味であり、その後の人生の糧になっていきます。
色んな体験を子供と共に楽しく、時には厳しく進んでいきましょう。
さて、本編ですが
今回は、小学4年後半頃から始められる新たに中学年代で忘れがちな私立中学の部活について、どのように進路活用を行うかについてをメインで話していきます。
進路選択の地域性
1,進路をクラブチームと部活で検討できる地域
2,進路をクラブチームと私立中学の部活、公立中学の部活で検討できる地域
(Jの下部組織に入ることが出来れば、悩む必要は無いので、ここでは触れません。)
この2つに分かれます。
2の活用が目立つ地域は青森、静岡、山口、神奈川、東京でしょう・・・
本題に入る前に、息子が高校年代に入ったこともあり、近い将来息子が直面する岐路が近づいている。サッカーを続けるべきか、否かについて
中学の3年は早いので、更にその先ので役立つ情報になってくれるのではないかと考えています。
以前から中学年代と高校の6年間で子供たちの育成を行っている高校も多くなっていますので
現時点で私が収集した、その予備情報も情報共有していこうと思います。
小学生(高学年4年~)から将来の進路を検討する際の情報(サッカー業界を俯瞰)
データから見る勝負何処は何歳?
サッカーで日本代表になるんだ!カッコイイ選手を目標に挑戦する子供たちを見ていると、一生懸命サポートしたくなるのが親心であり、私も同類なのですが
社会人を経験し、周囲の情報から色んな角度から物事を見ることが出来る大人になりました。
![]()
プロ入りする年代の18才以上はどのようになっているのか
プロ野球ではドラフト会議が有名ですが、年に育成枠を含め120人程度がプロ入りします。(高卒以上)
なのですが、1軍の選手登録を獲得することは並大抵ではない。
野球より、スポーツ人口の多いサッカーはどうなのでしょう。
では、Jリーグ
2022年におけるシーズンでJリーグでの登録選手は
J1は555人、J2は668人、J3は536人、全カテゴリーの合計は1,759人だそうで(外国人を含む)
次にJリーグプロ内定・新加入選手数推移表
| 加入年度 | 合計 | 大学 | 高校 | J下部 | その他 |
| 2021 | 131 | 60 | 37 | 34 | 0 |
| 2020 | 196 | 107 | 27 | 62 | 0 |
| 2019 | 173 | 96 | 24 | 53 | 0 |
| 2018 | 110 | 38 | 24 | 48 | 0 |

こちらの情報は、上記サイトからの(出典)になりますが、プロ内定の数字等について確かな数字を掲載しているところは発見のですが比較的信憑性が高そうなので、この数字で話を進めていきます。
各年代を参考にしてプロ選手になるのは、年に150人ほどになります。
J下部の数字を高校年代として、およそ50%
大学年代が50%がサッカーのプロ選手になっている
| 選手数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 2020年度 | 増減 | 増減率 | |
| 第1種 | 139,480 | 122,999 | -16,481 | -11.8% |
| 第2種 | 173,135 | 169,062 | -4,073 | -2.4% |
| 第3種 | 229,537 | 205,771 | -23,766 | -10.4% |
| 第4種 | 269,314 | 253,745 | -15,569 | -5.8% |
(JFA出典)
サッカー登録第1種と2種の定義
| サッカー | 種別 |
|---|---|
| 年齢を制限しない選手により構成されるチーム Jリーグ・JFL・社会人連盟・大学連盟・高専連盟など | 第1種 |
| 18歳未満の選手で構成されるチーム(高校在学中含む) 高体連・クラブユース連盟・その他 | 第2種 |
(JFA出典)
勝負何処の年代は!
どうやら大学、高校が勝負何処の年代になると言うことです。
その年代までに仕上げていくことが、最終目標で
プロやトップアスリートになる確率は、どのスポーツでも狭き門です。
2020年をベースでみると
1種 122,999+2種 169,062 = 292,061人
そのうち、150人ほどがプロ契約を行う確率は年間でみると0.05%
およそ2000人に1人はプロ契約が出来ることになります。
改めて、勝負年代は高校年代が一つの目のチャンス、2つ目が大学年代となります。粘って社会人の年代も可能である。
ですので、小学や中学年代の成長期は、技術とポジショニング、勝負勘(経験)、パス成功率、ペナルティーエリア付近でのoff the boll(ボールに触れることなく、味方を有利な状態に持ち込む)そんなことを最大限成長させる時期
前回の高校サッカー全国選手権大会では、青森山田が優勝しましたが
他のチームに比べ、既に身体がプロレベルの身体に仕上がっている。
フィジカル、寄せの早さと、寄せ方の上手さ、常に味方が有利になるよう全員が献身的に働き、結果相手にシュートを1本も打たせない完璧な試合になりました。
試合開始から終わりまで一切妥協しない、攻守の切換えも圧倒していた。
あの試合は賛否両論ありますが、世界に通用するサッカーのように私は思えました。
息子がプロになるのであれば、あの試合に出ていた青森山田の選手の上を目標にしなくてはいけないと考えています。
多分、息子もそう考えているでしょう。
さて、次からが本題です
私立中学を選択する、メリット、私立中学を選択し、部活に入るメリットについて
私が今回この記事を書こうと思った理由なのですが、ジュニアユース世代の進路選択の話しをネットで調べると、クラブチームと部活について説明をされているものをよく目にしますが、部活の中でも私立中学のことに触れるものを見たことがありません。何故なのか不思議だったのです。
保護者目線からすれば、公立の授業料と私立の授業料をまず、考え生活の資金問題が浮上しますが、それ以外は多くのメリットが存在する。
今になって思うと息子がトレセンの練習に出ていた時、指導者に進路相談したことがあるのですが、クラブチーム以外に私立中学の部活の話も出ていました。ただ、その時は受験対策の必要性から無理と判断している。
何故なら、長女が中学受験をしたので現実の体験からそう考えてしまった。
今は違います。
では、よくある進路選択の書き出し風にはじめていきます。
お子さんが「プロになりたい」と思っていて、保護者の方も、「この子には芽があるかもしれない」と思っている場合は、近くの中学では物足りない場合があります。この場合の選択としてはクラブチームになるでしょう。
お子さんが「プロ?無理でしょ」と思っていて、保護者の方も「サッカーは趣味でいいよね」と思っている場合は入学予定の中学の部活となる。
また、入学予定の部活では、弱すぎる、人数が少ない・・・どうすべきか
高校受験も先に待っているので、頃合いを見てサッカーを一旦休止して高校で改めてサッカーをさせるか。など
このように二つの狭間で悩んでいる場合もあると思います。
将来の進路については、小学4年生頃から子供のサッカーレベルが少しづつ見えてきて、周囲の子と比較し子供のレベルにあった進路のことを考え始める時期で
サッカー業界に詳しいご家庭は、将来へ向けた選択肢へのアクションを迷いなく進め始めます。
技術もあり成熟度が高い子は、J下部に合格するなど周囲が騒がしくなってきます。
この時期、将来を見越すのは大切なことなので、最良のサポートが必要なタイミングです。
クラブチームに入ってもいいけど、勉強が疎かになることも不安
→帰宅が10時くらいになり、まともな勉強ができない。
クラブチームで怪我をしたらどうなるのか
このまま公立の中学に行かせても、中学のサッカー部が弱い又は、部員数が少ないことを考えると子供の力量であれば強いチームが良いのではないか
など、不安は尽きない。
皆さんもご存じだと思うのですが、サッカー強豪私立高校の中学
ここが、手の届きづらい位置なのですが(そのように思えます。)
その選択肢についメリット、デメリットを交え、お話ししていきます。
実際にお会いした保護者の方からお話を伺っています。
あくまでもヒアリングは限定されたものですので、全ての私立中学に完全に共通すものではなく、傾向としてご理解下さい。
ただ、ここに書いてあることは、現実に存在し、こんな私立中学もあると言うことです。
ターゲットとなる私立中学でシッカリ指導者へ確認して下さい。
ここに書いてあることをベースに質問事項として整理し、確認していただければ幸いです。
●強豪の私立中高一貫校に進学し、中学時代はクラブチームに所属
(県内でも、県外でも構わない通えるところ)
有名大学の付属中学であれば、なおよい
メリット
・高校受験が無いので、3年間みっちりサッカーに打ち込める
・クラブチームの活動を優先したところ重度のケガをしてしまったケースやコロナ 感染拡大で、クラブチームを辞め部活へ転向
→クラブチームでも相次ぐ大会の中止や規制で、トップチームは大会で結果を出す必要性があり、必要最小限だが練習があった。
しかし、トップチーム以外は練習や試合が減少
中学の部へ転向したのは、サッカー強豪校もクラブチームと同様に活動規制があるものの、高校を見本にして中等部も活動は少ないが行われていた。
更に、コロナ対策が早く、オンライン部活として筋トレやミーティング、栄養指導セミナー(保護者を含めたオンライン)も行われていたそうです。
デメリット
・クラブチームは、近隣の中学校の日程から活動日を決めていることがあり、クラブチームの試合が土曜に入ってしまい土曜日に授業を休まなくてはいけなくなった。(試合に出ないと、Bチームに落とされてしまう可能性がある、レギュラーを取られてしまう。)
・クラブチームの月謝と私立中学の授業料のダブルパンチで資金難となる
少し、メリット、デメリットを並べましたが、最大の問題は
受験をどうするのか?
小学年代でサッカーを真剣に取組んだ場合
全小は12月まで、最後の少年団大会は2月だ!受験の準備が全くできない!
更に合格するには最低でも6年生の1年を勉強に当てる必要があるだろう!
無理!選択肢に入れられない。(昔の私の考えでもある)
確かに、そのような結論になることも分かります。
ただ、よく見てみると全小の県予選で上位に入っていたチームの選手や
最後の少年団大会で上位にいたチームの子が、私立中学に進学している現実があります。
私立中学受験は地域により異なりますが、1月の上旬から始まり2月の中旬には終わります。
こんな背景もあり、何故入学したのか不思議に思えるところもあるのですが
小学6年間サッカーをみっちりやっていながら中学ではクラブチームに通い、実際中学は私立に通っている子も存在しているのです。
ここで分かることは、強豪高校も小学年代で優秀な選手を獲得したいと考えてるということです。(優秀でなくても、素質がありそうであれば、中学に入れるよ!
そんな声が聞こえてきます。)
中学の部活に入らなくても別に構わない、クラブチームで切磋琢磨し、高校のフィールドで力を発揮してくれればいい。
また、クラブチームで問題があれば、部活に来い。
こんな取組も存在しているとのことです。
申し訳ありませんが、最大の問題についての説明はもう少し後でお話しします。
次に
●強豪の私立中高一貫校に進学し部活を行う。
ここでは、兄が公立中に通いクラブチーム、弟が強豪の私立中高一貫校に進学し部活で活動をさせた保護者がいたので聞いてみた。
中高一貫校目線のメリット、デメリット
メリット
【帰宅時間と受験】
帰宅時間は私立中学の方が1時間30分以上早く、帰宅
兄は高校受験勉強があるので、Offの日に塾へ行かせた
身体への負担はクラブチームより少ない。
通っていた私立中は、中間や期末テストで悪い成績だと強制的に補習授業に参加させられる。1時限目の前に0時限があり暫くの間、この授業に出ることになる。
後で、理由をお話しますが
この補習のメンバーは、弟さんと同様に私立中学のサッカー部に入部した部員が多かったそうです。
【指導】
指導者の資格(ライセンス)を持っている先生が顧問であり、高校の指導者がコーチに入っていて指導面はクラブチームと比べて遜色が無いように思えた。
基本実力主義なので、1年からスタメンに入る子もいた。
【トータル費用】
クラブチームでは、月謝+遠征代+合宿代+塾代
中高一貫では、授業料+遠征代+合宿代
強豪一貫中学はクラブチームが参加する大会にも出場し、活動内容はクラブチームと遜色がなく、遠征もクラブチーム並みだが遠征費は部活の方が安い
塾代を加えると
トータル費用は、若干一貫校の方が安かったとのことです。
【ケガ】
弟は試合中に骨折、顧問から練習は出来ることだけやれ!無理するな
最悪高校に行くまでに万全にしろ。
そんな声を掛けられ、スタメンから外れる結果になってしまっても、サッカーを続けていくことについて不安感はなかった。
兄もケガで離脱があり不安感は弟の比ではなく、無理をするところが見受けられ、辛い思いが強く残った。
【活動】
受験が無いため、高校入学までの期間は高校の練習に参加し、ブランク無く高校へ入学
大会は中高一貫校の私学大会が1月まで
関東(東京、神奈川、埼玉、千葉)
参考情報ですが、多くの子が高校受験をしている中、年末に開催している大会もあるので、これも良かったとのこと
デメリット
【試合数】
クラブチームと比較すると若干少ないように感じたが、部活で人数が限られていることもあり、上の学年の試合に出ることもあったので、レベルの高い子は試合数が多くなることもある。
【教育・・・】
部活だけでなく、生活態度や勉強の成績で一定の基準(顧問のジャッジ)があり部活に出さない事や試合に出さないことがあった。
(公平に厳格だったそうです。デメリットに入れましたが、クラブチーム目線で比べるとデメリットですが、人生ではメリットに入るでしょう。)
ここでの感心した話として、
中学年代よく耳にする。
友達に流されて悪いことをしてしまう。
友達をイジメる、物を取ってしまう。
そんな悪い行為を知っていながら、友達関係を維持するための流される行為を行ったことが分かっただけで
練習参加をさせない。などの罰を与えたそうで
その理由は、プロサッカー選手になることを目標にしているのであれば、周囲の悪い流れに同調してはいけない。
自分を守るために、また、人との信頼関係を壊さないために悪いことは悪いと態度で示せる人間に成れ。
自分の考えをシッカリ持てる人間になれ。
そんな理由からだったそうです。
確かにスポーツ選手の中には、海外まで行ってカメラを盗むとか、闇カジノに行ってスポーツ生命を台無しにするとか、そんな選手がいました。
非常に勿体ない。
追加のご意見をいただくことも出来ました。
人数を多く合格させるクラブチームや、小規模のクラブチームに入るより成長が見込め安心感がある。
確かにクラブチームの強豪には勝てないが、全てのクラブチームに負けているわけではない。
相手はセカンドチームかもしれないが・・・
セカンドチームであれ、トップチームであれ、中学の部活チームに試合で負けてしまうクラブチームは早めに淘汰しないと子供の成長においては悪である。
こんなご意見をいただきました。
また、追加で
クラブチームとの対戦は少ないが、静学中、高川中、暁星中、桐蔭中、栄中などなどの対戦があり、実質クラブチームの中堅以上のチームとの対戦は確保できていた。
だそうです。
余談ですが
一昨年前、少し騒がれましたが、埼玉県の新人選で部員17名しかいない私立中学が県大会で優勝。しかも2年生は6人しかいない。(11人は1年生)
県大会に出てくる中学の部員数は少なくとも1,2年で3、40人いる中
負傷者が数人出ればアウトのチームが優勝した。
決勝戦はTV中継され、メンバーの出身チームをみると有名どこが
そこそこ入っていましたが、あまり知られていないチーム名の方が多かった記憶があります。
指導力でチームを成長させたのかな・・・
話を整理していく上で、知っておいていただきたい内容に入ります。
私立中学に関係するサッカー強豪高校の組織について
・下部組織としてクラブチームを持っている強豪高校
・下部のクラブチームを持たない強豪高校
この2つに分かれます。
他に新たな取組として
この2つの成果はどのようになっているかと言えば、甲乙付けがたい。
下部クラブチームを持っている高校の目的は、6年間の集大成として高3に向けて育てる。実際に高校3年の選手権で出場する選手が全て下部の子とは限らない。
下部クラブチームを持たない高校は元々、練習会と称したセレクションで優秀な選手を獲得すると共に、有力選手の発掘は通年行われている。(これはリクルーティングと称しているようだ。)
2つは組織的な違いはあるものの、コロナの影響もあり上手く機能していない
リクルーティングやセレクションもうまく機能しないご時世であり、6年間の育成を目指し中学の部を底上げする動きを取らざる負えない状態にもなっている。
下部クラブチームを持っている高校は、優先して高校に上がって貰えると思っていても、トップチームから漏れてしまった子は高校へ行ったとしてもレギュラーは獲得は難しいと判断し別の高校を選択する結果となる。
(実際、あのチームであの子はBチームだったの?と言う子を見たことがあります。何かしら理由があると思いますが、チームが変わり指導方法も変わったことで覚醒したような動きの子をみたことがあります。逃した魚は大きいように思えた。)
一方、下部クラブチームを持たない高校は、基本実力主義なので部活があろうがなかろうが、関係ない。
ただ、中学の部に在籍していた子、又は部に入らず他のクラブチームに所属していた子はチャンスを早く与えてもらえる。
学校教育がメインでもあるので、指導者に名前を覚えてもらっているだけでも有利に働く。ただ、力量を中学時代に判断し高校では別の部へ加入する子もいる。
色々と長く、説明してきましたが、クラブチームを持たない強豪高校の中学サッカー部も選択肢としては、ま~ありだと思っていただけるような事柄をお伝えしてきました。(屁理屈ぽいところもあるかもしれませんが、ご了承ください。)
もういい!分かった早く、最大の問題の解決方法を教えろ!
受験対策はどうするのか!
そんな声が、聞こえて来そうですので
私立中学を選ぶ際の留意点(手法)
ここからは、少々歯切れの悪い文章が含まれますが、ご了承ください。
・中学入試は1月か2月に実施されることもあり、クラブチームのセレクションも終了し、既にどのチームに入るか決まっている時期になります。
時間軸で考えるとクラブチームの加入が先になるので、私立中学の選択肢が無くなると思いがちですが、そうではないことを知って頂ければと思います。
前の話で、弟が私立中学に入った子が登場したのですが、その子の話になります。クラブチームのセレクションを受け2つのチームで合格
その中から1チームに絞る分けですが、その際クラブチーム側に中学受験があり
その結果が出るまで入団の回答を延長して貰うことを相談したそうです。
その結果、クラブチーム側も了承したそうです。
(私も、似たような交渉をしたことがあるのですが、クラブチームの回答期限延長を申し出ると結構な確率で了承していただけるように思えました。確実に延長できるものとして、J下部の選考途中であること。中学受験など生活上で将来、練習参加が不可能となる可能性がある場合。
実際に私も1回しか交渉したことが無いので、確かなことは言えませんが、所属している小学生チームに悪い印象を与えてしまうと次年度からセレクションを受けに来てくれなくなる不安がクラブチームにあるかもしれません。また、悪評が立つような行為は避けているのでしょう。)
一方、私立中学側ですが、下部組織としてサッカー部の強化、育成を考えていますが、クラブチームのセレクションが先にあり安心を選択するのが人間の常なので私立中学の部活を選択することを考える人が少ない。(私立中は良い選手を取りたいが、劣勢)
こんな状態ですので、少しでも良い選手を確保するために可能な範囲でサポートしてくれる顧問が多い。
部活見学と言う名目で、早い段階(小5くらい)から見学(体験が可であればそちをお進めします。)に行くと良い。
準備している中学は、4号ボールを持っている場合がありますが、自分の使っているボールを持参しましょう。中学から5号ボールになりますので、小学生の段階で
5号ボールは大きくて、重い。
見学(練習会)を受け入れているところを教えてもらったので一例として、紹介しておきます。

練習会に何回か参加し、お子さんがその体験で、クラブチームや地元の中学の部活より、私立中学の部活でサッカーをやりたいと思う気持ちがあれば、それをそのまま、顧問に相談することです。
顧問からすれば練習会を実施し、ここでサッカーをヤリタイ!と思ってくれる子を探しているので、サッカーレベルはどこかのクラブチームのセレクションで合格出来るレベルを練習会でアピールできれば脈ありだと思います。
(えーそんなんでいいの?と思われますが、そんな感じだそうです。)
さて、受験対策のところになるのですが、学力の足切りがある学校も存在しますが、サッカー強豪高校の練習会(セレクション)と中学も同じ考えがあるようです。
まず、高校のセレクションの仕組みを理解して下さい。
私立強豪高校のセレクション合格者(練習会の表現を使うところがある)は全員入学試験を受ける。
テストの結果を問わず、受験合格を出す。
この権限は顧問にある。
セレクションで合格した多くの子は、この内容です。
セレクションでの合格は、合格保証を貰うだけと考えて下さい。
特待制度について
セレクションで50名ほど合格したとして、特待生か準特待で入学できるのが5,6人で10人はいない。
内訳として特待生は1人いるかいないかで、入学金免除や授業料の一部免除の準特待が数名程度であることが現実です。
特待生や準特待は、所属するクラブチームの責任者へ練習会参加を依頼し、リクルーティングの一環として、練習会終了後クラブチームの責任者へ特待生として受入れたい旨を伝えつつ、他校へ行かないよう慎重に事を運びます。
高校の余談ですが、知っておいた方がよいので(私が新たに知ったことです。)
セレクションで合格した場合、強豪校ではスポーツ課的な名称(保健体育科とか)のクラスに入ることになります。一般入試の子とは一緒にされない。(学力の差があるので、一緒には出来ない)
但し、合格は保証し、一般試験で成績が良ければ希望のクラスに入れる高校
一般入試を希望した場合、合格を保証しない高校がある。
また、高校の考えとは別に、スポーツ課でなければ入部出来ない制度を取っている部もあるので注意が必要。
私は、え?どうゆうこと?なんでそうなるの?
この話を聞いたとき、そう思いました。(特にこのご時世でもあるので・・・)
理由は、高校の中でも強化部と言うものが存在していて、部活で全国制覇を目標にしている部活とでも言うのでしょうか。
そのような部は、学業より部活が優先できるスポーツ課に入ることが義務付けられる。
私個人の考えでは、大変申し訳ないがスポーツ活動が制限されるこのご時世でこの選択は無い。スポーツもまともに出来ない、勉強も中途半端な状態になってしまう。
すみませんそれました。
ここからが中学受験対策
ほとんどの私立中学では、特待制度がある
特待制度の多くの基準は、成績優秀者と記載があり、学業に限定するところもあるが、成績優秀者の記載で済ませているところも多い。
中学の顧問の権限は、特待レベルは個人競技で全国優勝しているとか、全国ランキング4位以内など、結構ハードルが高い。
団体競技になると、全国大会出場程度では獲得するのは難しい。
なので、入学保証の権限を行使することになる。(これも一つの特待と考える方が納得がいくと思います。)
普通に受験対策を行い受験を行うと、小学4年から塾に通わせると200万ほど掛かるとのことです。それが無くなる(下記の栄光ゼミナールサイト参照)
ですので高校同様、受験料を支払い入学試験を受けなければなりませんし
授業料も支払わなければいけません。
クラブチームの費用と比較することも必要でしょうね。

青二才さんのブログを参照ください。
【入学金、年間授業料等の目安:栄光ゼミナールのサイトを参照下さい。】
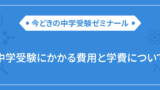
余談ですが、中学受験の経験談
私の長女が中学受験をしたのですが、バドミントンの小5で関東大会レベル、6年も継続すれば全国も見えていましたが、勉強とスポーツを両立するのは無理と判断し6年生の1年はバドミントンから離れました。
小学4年から塾に通い、5年ではバドミントンクラブの参加状態も半分の量になり4年生から受験まで、200万掛かることも頷けます。
また、受験では滑り止めを含め、4校は受験しますので受験料だけでも10万を超えていきます。
ですので、入学保証の有効性は個人的に見ても魅力的です。
私立中学攻略のまとめ、活用と過去の例
練習会はセレクションと同義語と考える(イコールではない、大人の事情が含まれている。)
ただの練習会はセレクションの要素が含まれていて、セレクション合格は入学保証を獲得できる。(この条件の中には、受験1回でOKの場合と、2回目に合格を出すところがあるようです。)
早い子だと、小学5年で合格を獲得していて、小学6年の時にみっちりサッカーに打ち込める。
何故、この仕組みが表に出てこないのか考察してみた
まず、今まで書いてきた内容を振返って欲しいのですが、進路選択の候補として上がりにくい要素が多いことが上げられます。
また、内定を貰っていても保護者は子供に内緒にする傾向がある。
周りの人にも言わない。(何故なら、受験に対しての不安感を解消できていない状態にあるから合格するまで口外しない。)
周囲には合格後に伝えることになるが、中学サッカー部のセレクションに合格したという表現にも至らない点があり、説明が難しい。
こんなところでしょうか。
この私立中学を活用する方法は、ある意味利点が他にもあって、この話を整理していくと、4種チーム全員が一つの私立中学に進学出来る可能性があり、最長12年間共に歩むことが出来ることになります。
全員は難しいとして、気の合う子だけでも良いのではないでしょうか。
入学後の学業に対する不安
中学の場合、高校のスポーツ課的なクラスはほとんど無く、塾に通い受験勉強をしている子が殆どです。
その中で、勉強についていけるのか不安になるところです。
前のところで、入学後の補習授業について触れましたが、保護者の話が面白い
ゼロ時限目の補習は、1時限目の前と授業が終わった7時限目にも設定されているそうで、登校する時間は通常の子達より1時間ほど早くなり、最終時限後の補習を受けると部活に参加する時間が短くなる。
現実その補修はスポーツ推薦の子達が集まる場なので、子供たちは自ずと「バカ集団」と命名していたそうです。部の顧問からしてみれば、早く「バカ集団」抜け出して欲しい
また、子供達も勉強が大嫌いなので、補修授業を受けたくないので「バカ集団」から抜け出そうとする。
誰がホントのバカか!ホントのバカにはなりたくないので、勉強をするようになる
その妙な離脱意識が競争心となり中学2年の中盤くらいから「バカ集団」の存在が無くなってしまったそうです。ある意味「バカ集団」は伝統になっているそうです。
スポーツ推薦で入学しても普通に勉強できる子は、初めから「バカ集団」には入らない子も多いようで、中にはバカ集団から抜け出し学年で上位成績者へ進化する子が出てくるのが不思議だとコメントがありました。
ですので、入学後の学業不安はあるものの、本人の努力で遅れを取り戻せる環境を学校側だ用意していることが多いそうですので、あまり心配しなくても良いのではないかと思う次第です。
この点も、私立中学の指導者に質問し、学業の底上げ環境についてお聞きすることをお勧めします。
不安の解消については、私立中学の取組によって変わりますので、質問を精査し
不安を少しづつ取り除いて下さい。
部活動の生徒たちに聞くことも可能だと思います。
中学生年代で、クラブチーム、公立中の部活、私立中学の部活の3つの選択肢を検討の中に入れ、お子さんに最良の選択になれば幸いです。
ここからは、おまけとして高校年代の保護者から最近私のところに入った愚痴を整理してみましたので参考にして下さい。
中学年代でクラブチームを選択した保護者の後悔を取り上げます。
最良の選択を行うために頭の片隅に入れていただければと思います。
クラブチーム選びでの注意点
息子が高校年代に入り、高校の部活には様々なクラブチームから子達が集まってきているのですが、この年代でクラブチームの選択を間違えたとの話を聞くことがあります。
その内容について少しお話します。
・希望していた高校のルートが無かった
・高校へのスポーツ推薦を得ることは出来たが行きたくない高校なので一般受験で 志望校に入ることにした。(指定高制度がクラブチームに存在しているのか?)
・中学では勉強の成績が優秀だったので、クラブチームへ推薦等を相談していたが結局推薦先がスポーツクラスに強制的に入れられることが判明し、そこ以外推薦は無いと言われた。
ちなみに、この子がレギュラーで所属していたクラブチームは県内トップクラスの強豪でした。
・推薦先は確かに強豪校高だが地方の高校しかないと言われた。
など、比較的似通った話・・・
もしかすると他人事のように書いていて、私のものが含まれているかもしれない・・・
としあえず、他人事として私のところには、何故か愚痴の話が多く入ってくる
クラブチームの多くは、説明会でサッカーでの進路としてどこぞの強豪校のルートがあるとか、サッカー推薦でほとんどの子が高校に入学している。
そんな実績をアピールする。
クラブチームのセレクションで合格し入団した後、保護者は高校入学を確保したと安堵するが結果的として理想的の進路にたどり着けない状況も多くあるようです。子供が中学生にもなると、心身共に成長しているので親に対して不平は言わない。
自分の親も色んな情報を持って来て、お金も出してくれて、自分がやりたいようにやらせてくれた。不平不満などは言えるわけもなく、現状で選択できる道に進む。
子供はこんな感じに育っている。
クラブチーム選びも慎重に情報を集めてください。
また、このコロナ過の中、進路選択は従来より難しいように思えます。
コロナによって変わった高校サッカー部のセレクション
一昨年前、所謂息子が高校を決めセレクションを幾つか受けさせていただきました。
今も未確認で申し訳ない限りなのですが、この先もコロナの影響が続く場合に注意が必要ですので、お伝えします。
コロナ前のセレクションは日数を数回分け、セレクションで合格者を決めていく
1次、2次、3次と行い、セレクション合格者や特待生の決定を行っていたようですが、これが変わっていた。
なんと書類審査で練習会に呼ばれた者は、合格となる高校がほとんどだったようで
通常のセレクションと思い、練習会に呼ばれたが2次へとも言われず勘違いして不合格と思い込む子もいたようです。
これは、クラブチームの責任者から伝達することなのか、高校側の周知が甘かったのか分かりませんが、注意が必要です。
思い込みではなく、このご時世ですので、合格の基準などをシッカリ確認ください。
おわりに
今回私なりに、コロナ過の影響もあり、どの年齢が勝負どころか
そんな話を始めに持ってきましたが、息子の年代から始まり、コロナの影響は多くの負を持ち込み、今も続いている。
息子の代だけが修学旅行やインターハイの中止に留まり、コロナ発生から1年程度で終息を迎えるかと予想していた時期もありますが、新たにオミクロン株に変異し、亜種としてBA1からBA2への移行が世界で起こっている。
現在、第6波に突入しているがBA2への置き換えで、第7波へ突入する可能性を秘めていることや、更なる変異の可能性もあり出口がいまだ見つからない。
ウィルスの性質上、徐々に感染拡大の方向へ変異しつつ弱毒化に向かうと言われていますが、それでもワクチンの効果が薄れる、治療薬として有効なものがいつ現れるかも不透明。
私も経験した、息子の中学年代は悲しい思いしか残っていない、同様にこれから中学年代に突入する方々を思うと、少しでも選択肢の情報を増やしつつ、最良の選択をしていただければと思うことと、勝負所は高卒や大学年代であることを認識していただき、何があっても諦めないで取り組む方が1人でも増えればと思った次第です。
私の環境も息子が高1ですので、あきらめない精神で進んでいきますので、共に歩みましょう。
今後ともよろしくお願いします。
最後に、本ホームページからの問い合わせは、上手く機能していないようですので、くま太郎のTwitterで個人的な質問はお受けしようと思いますので、個別にDMを頂ければと思います。
また、返信にはお時間をいただくと思いますがご了承ください。
あと当たり前ですが、悪質なものは無視させていただきます。





















コメント