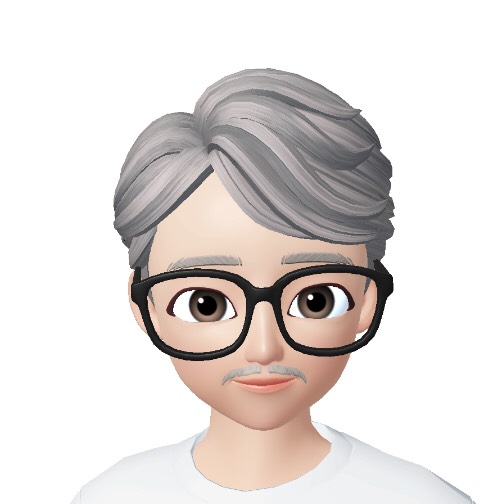 息子がサッカーを始め、数年たつとセレクション?
息子がサッカーを始め、数年たつとセレクション?
そんな話が出てきたり、素人の私には何のことか良く分かりませんでした。
既にお兄さんがサッカーチームに所属していて
少年サッカー業界の仕組みが分かっている方はあまり意味のないブログです。
子供がサッカーをやりたいと言っているけど少しでも知識が欲しい。
そんな方には是非読んでいただきたい内容となります。
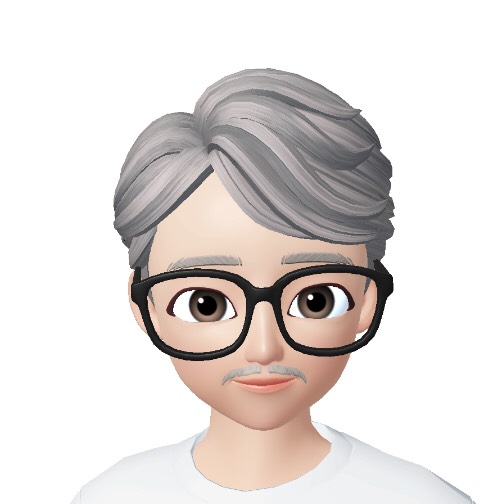
そんな話が出てきたり、素人の私には何のことか良く分かりませんでした。
既にお兄さんがサッカーチームに所属していて
少年サッカー業界の仕組みが分かっている方はあまり意味のないブログです。
子供がサッカーをやりたいと言っているけど少しでも知識が欲しい。
そんな方には是非読んでいただきたい内容となります。
チーム選びで大切なこと
息子がサッカーを始める切っ掛けになったのは、単なる流れで
仲良くなった子に誘われたのが始まりでしたが
長年たずさわり、サッカーを真剣に取組ませるのであれば
「地域のサッカーチームやスクールの状況を理解した親のサポートは非常に大切である」
今思うとこう思うのである。
私の場合、振返ってみると後手に回っていて反省しかない
特に息子の所属したチームは、保護者の関与を最小限にしていた運営なので
保護者のコミュニケーションが少なく、情報があまり入ってこないことも原因だったと思いますが、早い段階でお子さんの目標と道筋をザックリと計画を立て
保護者として、背中を押したり、導くことが大切だと私は思います。
確かに「子供自身に決めさせる」との考え方も否定しませんが
実際は、同じ時間を使って子供にとって最適な成果に繋がる環境はどこなのか?
と保護者が考え、子供の自主性を尊重しつつ誘導していく
私の感覚ですが、小、中、高と見て目立つ子は、保護者がサッカー経験者であったり、兄弟がサッカーをやっていたなど
保護者がサッカー業界で経験していて、既にサッカーを行う上で道筋が見えている
末っ子は兄や姉の影響を受けて同じスポーツを習い始めるケースが多く、さらに彼らをよく見て育つため要領がよく、親からのプレッシャーも比較的少ないため、のびのびとプレーして才能が開花するパターンが多いもようです。
サッカー関係を経験している保護者と私では、既にスタート地点で後れを取っていたと今では思えます。(実際当時は何も気づいていなかった状態です。)
予め知っていれば、情報収集や方向性を決める助けになることを祈りつつ
進めていきます。
特に保護者がサッカー素人で、サッカーを行うのが1人子供の場合は参考になると思います。
![]()
少年サッカーチームについての基礎(チームの種類など)
サッカーチーム選びについて将来直面する課題なども掘り下げていこうと思います。
別のブログでも触れていますが、公式戦にエントリーできるチームは大きく分けて
2種類あるとお伝えしました。
それが、クラブチームと少年団チームですのでその説明を交えて進めます。
J下部は別扱いとして、今回は触れません。
クラブチーム:クラブ起源とスクール起源
少年団チーム
チームを選んだ傾向
チーム加入後の課題
私の場合は、右も左も分からず、息子がスクールで知り合った子と同じチームに入ったので何の悩みもありませんでした。ま~無知の極みみたいな状態でした。
もし、あの時に今の知識があれば違うチームを選択していたかもしれません。
ここでは、当時の私レベルで右も左も分からない方が
チーム選定で、あらかじめ知っていてよかった~
これを知ったことで、将来のイメージと適合するチームが見つかりました。
そんな人が1人でも増えれば大変喜ばしい限りです。
また、小学年代で納得の行く状態で終わることが出来た❣
そんな人が出れば、さらにうれしい限りです。
ですので、サッカーチームを選ぶにあたっては、1~3年生で変化する傾向も書いていきます。
チーム選定だけでなく、その後に直面する課題も予め知っておくことで、準備も早くできると思います。
確かに、そうなって行くんだろうね~、うちはどんな状態に将来なるのかな~
ではなく、うちはこうなるように取組んでいく。
そんな前向きな展開になっていただければ嬉しい限りです。
サッカーチームを選ぶ上でまず、チームの種類
クラブチーム:クラブ起源とスクール起源
クラブ起源であれスクール起源であれ、この団体は専属のコーチ陣を抱えています。
クラブ起源
中学生年代の子を育成し、J下部や強豪高校などへ選手を送り出すことを目的とた組織で、新たに小学生年代のスクールやチームを新設しています。
中学生年代の子をクラブチームが受け入れる場合には、セレクションがあります。
原則下部組織の小学生チームに所属していても、セレクションに合格しなければいけない。
スクール起源
小学生を受け入れていたサッカースクールが新たに少年サッカーチームを新設したものになります。
スクール運営は子供のレベルに合わせて指導しているので
上のレベルを保持していなければ、辞められてしまう(収入の減少)
最低でも2段階程度のレベルが存在している。
スクールの場合には、このようにレベル分けとスクール生徒の中でレベルの高い子だけが入れる少年サッカーチーム(クラブチーム)へ加入する方式を取っているところもあるようです。
少年団チーム
一番多いのが、少年団チームで全国の少年サッカーチームの8割くらいがここになります。
多くは、地域の町内会3つか4つくらいの範囲や、小学校2,3個で1チームを形成し指導者が経験のある保護者であったり、昔からの重鎮が時間のある限り、活動を支える。
そんなチームですので指導力や育成についても、千差万別です。
ただ、少年団チームの中にも、全国レベルのチームも数多く存在しています。
![]()
チームを選んだ傾向
①強豪チームに入れて、レギュラーになれなくても、チャレンジさせる。
②近所のチームに入れて、上のレベルにいけそうであれば、移籍させ上のチームへ
③子供のレベルで、レギュラーになれるチームでよい
④流れで子供が入るところが決まった
今まで、お会いした方々をみると、最初は大体この4つです。
チーム加入後の課題
チーム選びで一番多いのが
④流れで子供が入るところが決まった。
私も同じですが、正直言って子供が楽しく体を動かせればいい。
そんな感じだと思います。
しかし、2年、3年、4年とサッカーを行っているうちに
②上のレベルにいけそうなので、移籍させ上の(強い)チームへ
③子供のレベルで、レギュラーになれるチームでよい
の2つの考えに分かれ、
更に⑤チームが合わないので、別のチームに移る。
と言うのが加わります。
多くの方が、最初に所属したチームに残る傾向にありますが、 ![]()
⑤チームが合わないので、別のチームに移る。
移る、辞める等の理由には
・レギュラーになれるチームへ移籍
・試合の出場機会を増やしたい。
・指導方法が納得できない
・運営方法に納得できない。
など色々な理由が重なることと、
辞める場合には、建前的な理由で辞められることもあり、
本当の理由はそのご家族でしか分からないケースが多いでしょうね。
私も、息子が5年生の半ばころ所属チームに対する不満が爆発寸前までいったことがあり
「息子にサッカーいつ辞めてもいいぞ。」と言っていた時期があります。
サッカーは、コンタクトスポーツなので、打撲や骨折などは日常茶飯事的なものですが
息子も、ご多分に漏れず、明らかに身体の限界が近く、そこに捻挫(重い靱帯損傷)
をしてしまった事があり、私から指導者へ負傷の状態を話し試合出場を見合わせ
体力の低下を抑えるため軽度のトレーニングとして様子見をお願いし、チームのコミュニケーションもあるので、通院以外は練習や試合にも同行させる旨を伝え
コーチはこの話を了解しました・・・が
そんな時にちょっとした大会があり、観戦に行った保護者から、息子が試合に出ていると
連絡が入った。
約束が違う!何故出場させたのか説明させたことがあります。
これは不満につながる一つの例ですが、チームへの不満は多岐に渡ります
不満は積み重ねられ、限界を超えるかどうかなのでしょうね。
どこのチームにも起こりうることであり、特にスパルタの強豪チームでは
起きやすい事柄だと思います。
そんな中、移籍を実行せず、我慢して残留する理由について知っておきましょう。
残る理由(一般的なチーム):移籍したいが結局残る理由
・今まで、お世話になったから。
・辞めると人数が足りなくなって迷惑をかける。
・お父さんが保護者コーチをやっているので、チームに迷惑がかかる。
・レベルの上のチームに行ってもレギュラーになれない。
・子供がチームメイトと最後までやりたいと言っている。
残る理由(強豪チーム):強豪チームに所属していた場合
![]()
![]()
・このチームでは、絶対にレギュラーに成れないけど、他のチームに行っても強豪チームから来たと期待される。~期待外れ~と思われるのも・・・ 面倒なのでこのまま
・練習や指導が厳しいけど、これに耐えたことは先の人生でよい経験となる。
・小学生時代では、身体的に不利な状態であったが、練習試合で強豪と対戦した経験が将来の糧になると信じる。
・子供がチームメイトと最後までやりたい。
こんな理由が見受けられます。
比較的、子供本人というよりは、義理、人情や世間体も影響していることが分かります。
移籍について
子供が真剣にサッカーに取組むと、その力量はみるみる変わっていきます。
真剣に取組む場合には、チーム以外にスクールで技術を磨くことは、不可欠ですが。
小学3年生くらいになると、サッカーのレベルと身体の成長具合も見えて来ますので
チーム選びは、もしかするとその時点が一つのポイントでもあるように思えます。
新たなチームに加入し、チームメイトとのコミュニケーションを6年生までに整える時間が必要として、3,4年生年頃に子供の適性をもう一度見直すべきなのでしょうね。
また、2,3年でその地域のサッカーに携わることで、他のチームのレベルや運営方法も情報収集できると思います。
お子さんの性格やチームでの立ち位置や子供と話し合いながら最良の環境を見極めが必要ですね。
最後にすでに蚊帳の外となっている今の私であればどうするか。
まず、私の場合目標を設定します。
(子供に話すかは別として、誘導する方向性を決めます)
例えば、J下部のセレクション合格を具体的な目標とする
①周辺情報から指導方法が良いサッカースクールに通わせ、技術の向上を行わせます。
スクールは、集団生活やチームのコミュニケーションの馴らし、として
早めに入れます。年中さんくらいから遊び感覚で入れてもいいと思います。
②やはり、1年生でサッカーチームに入れる。
・指導者は、実績を残していること
・立地条件で子供が将来1人で通えるところ
・その中でも強いチーム
(クラブチームでも、少年団でもよい。同世代の人数が20人くらいいると良い)
・保護者の当番制が無いところが嬉しい。(必要最小限のサポートとしたい)
※勉強もスポーツも同じで、優秀な指導者がいるところ。
③遊びレベルですが、両足でボールを蹴れるようにする。
利き足は、自然と分かりますので、極力反対の足で蹴らせる。
保護者として小学2、3年生で子供の力量を見極め、1年スパンで次の方向性を見極め成長できるような環境を決めていく。
こんなところです。
理由については、本編では控えさせていただいて
別に強豪チームの傾向などについて、自分なりに共通点的な話を考えています。
そこで、強いチームを選ぶ理由も含まれますので見ていただければと思います。
多分、弱いチームの指導者に見ていただいても、参考になる内容になると思います。
子供の成長や、適正などを早く見極め早めに別のスポーツに転向することも視野に入れていただければと思います。
何故なら、サッカーは他のスポーツと比べると、開始できる時期(2,3才から開始できる)が早く、手軽に始められる特性があります。
よって、サッカーはスポーツ人口の中で、野球を抜かし1番の競技人口をあっという間に確保してしまいました。
小さいときから、経験したスポーツを捨てることは強い不安が生じますが見極めが大切になるのですが、お子さんが集団競技に向いているか個人競技に向いているかが一つの判断基準になるでしょう。
お子さんが、最適な道を進むことが出来るよう願いつつ本篇は終了します。
どうもありがとうございました。






















コメント