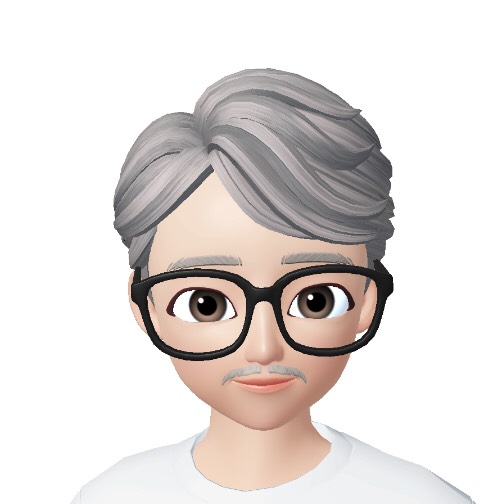
少年サッカー(1~3年)レギュラーを獲得するには-9年前から3年分日記-では
レギュラーに成るための評価ポイント(指導者は公平に評価しているようだ。)
やトップチームのミッション
更に、指導者の考えと、子供と保護者の考え方が一致していないと色々な誤解を招いたり、チームを辞める子も出てくることを話してきました。
今回はその続編になります。
ここでは、強豪チームのチームを仕上げていくところまで、素人目線で
最終学年で、精神面、チームの層の厚さを構築するには
最終学年での仕上げ(戦術の叩き込み)
こんなことについて分析したことをお話ししていきます。
最終学年で、精神面、チーム層の厚さを構築するには
強豪チームは、最終学年に向けたビジョンの上での指導が行われているように思えました。全国を制覇するには、子供たちの層を厚くする必要性から、子供たちへの熱い指導が行われます。
その言動を暴言や鼓舞、時には威圧のように思えるものも存在します。
ある子はインターバルの時、終始説教をされていて、その保護者は「酷い言われようだ」とぼやき(怒り)、逆に補欠の保護者は、「うちの子は言われないので」と羨ましそうに慰めなのか本心か分からない言葉も出ていました。
その言動をどのように解釈するかは人それぞれになりますが、子供の成長のためのように思えます。
(私の時代では、ある意味暴言レベルは当たり前だったので、やる気スイッチを入れているのかな~そんな感じで見ていました。)
改めて、レギュラーに成るための評価ポイント(公平な評価)は以下に記します。
評価ポイントを中心にチーム全体を最大限に成長させる指導をしていたと思います。
・相手より先にボールを触る(常に先、インターセプト率が上がる)
・テクニック(ドリブル、パスセンス、視野の広さ、意外性)
・怖がらない(ボールが顔面に当たろうが、逃げない)
・1対1で負けない
(1対1で負けないのは当たり前1対2や1対3で、すり抜けるテクニック必要性
ダメな時は適切なパスで有利な展開に持っていく)
・ボールを敵に当てない
(少年サッカーの場合、敵に当てたボールがカウンターになることを防止)
・転ばない (追加)
・ボールを自分からラインを割らない
・FWへボールを出せ
これらの項目で、試合中に無意識、反射的で冷静にプレー出来、レギュラーを守るには、試合に出ているときには手を抜かず、全力で挑む。
プレッシャーを掛けるとき、ボールを追うとき、自分の役割を果すためには全力疾走が基本です。
行動で迷いも排除、行動の遅れる子はスタメンから外される。
そのレベルまで指導者は持ち上げていきます。
(指導が上手いのか、凄いのか・・・感心しました。)
感心した指導のポイント
強豪チームには、こんなチームもありました。
キャプテンを置かない。
大会キャプテンやゲームキャプテンは置きますが、実質のキャプテンは存在しない。
重要な試合以外は、円陣を組まない。
真剣モードに入るスイッチとして、有効ですね。
通常、どんな試合でも円陣を組むチームは多いと思いますが
指導者目線で円陣を組むほどの相手ではない!
それを子供達も暗黙の了解で認識している。
円陣を組まない試合は、逆に絶対に負けてはいけない試合との一体感が生まれる。
また、ベンチメンバーを全員試合に出すだけの余裕ある試合を求められていることも認識するので、真剣モードは変わらない。
こんな使い方もあるんですね。
層を厚くしないといけない理由
やはり、高学年になると怪我も多くなります。
その際にも、層を厚くしておかなければ、勝ち残ることが出来ない。
また、全小の時期はインフルの危険性もあるので、サブメンバーも重要になります。
また、チビリンピックでは3クールで試合が展開され、選手は2クールしか出れない
由緒ある大会もあるので、これに対応できるチーム創りを求められる。
チビリンピックの試合ルール(3ピリオド制) ★ 選手の交替:第1ピリオドと第2ピリオド間では選手を総替えすること。
★第3ピリオドは交代自由とする。
★同一選手の出場は最大で2ピリオドまでとし、3ピリオド全てに出場することはできない。
★ 延長戦については前後半で同一選手の出場を可とする。また、自由な交代を適用する。
最低16人必要で、第3ピリオドがベストメンバーになる仕組み
独り言だが、小学生年代はこのルールであれば多くの子供たちの出場機会が与えられるのでいいように思える。
最終学年での仕上げ(戦術の叩き込み)
5年生までの地道な、指導は6年生から仕上げに入ることが分かりました。
メインはトップチームになるのですが、チームとしての本来のフォーメーションと、戦術が徹底されるとともに、適材ポジションの固定化が進んでいきます。
息子の入っていたチームが例なのですが、紅白戦を通してトップチームに戦術を叩き込みチームが完成していくのです。(3,4か月みっちりやりつつ、全小予選まで進化する感じでしょうか。)
マイボールになった時、そのポジションからどのポジションの誰に出すべきか。
また、受側の子が敵に背を向けた状態であれば、誰に落とすのか。
攻撃態勢に入った時のパターンを出来る限り理解させ、ビルドアップ時に最良の形で攻めあがれるよう練習を重ねます。
紅白戦で細かくチェックし、ダメな状況が生じたときには一旦試合を止め、そのシーンを再現するように、パス出しから何故ダメだったのか最良の形を全員で確認していく。
そんなことを、繰り返すのです。
(最近では、戦術確認の練習はプレーを止めない指導方法が推奨されていると話を聞いたことがありますが、どうなのでしょうか。)
また、固定されたポジションであっても、相手とのマッチアップで不利になることも想定されるので、身体の大きい子と小さい子を入替え、別のポジションも練習させます。
これが結構細かく、いつになく真剣な練習になります。
この戦術練習がどの程度まで熟成したかは対外試合や、大会で成果が表れるのですが
レベルが確実に上がっていることを実感できます。
特にサブメンバーであったり、Bチームのメンバーであっても、この戦略を少しでも理解するよう心掛ける必要があります。
練習の時間帯は、次世代の5年生と同じですので、5年生も一緒に鍛えている状態になります。
まとめ
サッカーの上達とレギュラー獲得に向けた取り組み
素人目線で小学年代の指導について、低学年、高学年に分けてお伝えしてきました。
レギュラーを勝ち取るにはチームや指導者がこんなことを考えているようだ。
なので、レギュラーを勝ち取るためにスクールに通わせ、レベルを上げたり
子供とビデオを一緒に見て反省したりを繰り返してきました。
あまりダメ出しをしすぎると、良くない。
駄目だしすぎて一緒にビデオを見なくなった時があります。
何を今鍛えるのか、目標を持って取組ませる誘導することが大切
チームや指導者の指導方法で、保護者のフラストレーションが溜る
6年間を振り返ると、指導者は6年後のことを視野に入れながら指導していて、素人保護者の私は、その時のことを考えるのが精一杯だったのかなと思う部分も多々あります。
途中で指導の厳しさや、保護者目線と指導者目線での食い違いによって辞めてしまった子もいました。
現に私も、辞めさせようと思ったこともあります。
子供にサッカーを続けさせるとき、必ず辞めさせようとか移籍しようとの感情は生まれるものです。
ですが、その判断が間違いでないことを祈るばかりです。
子供のサッカー上達も大事ですが、怒りが込み上げてきたときに一歩引いた位置で自分たちや指導やチームを俯瞰してみる時間を作ってみてください。
最後に、小学年代での吸収力は非常に大きいものですが、成長期では個人差が大分ありますので、焦らず見守りましょう。
息子は小学6年で身長148センチ、中3で170センチになりました。
もう少し、デカくなってほしい。
皆さんのご検討を心より、願っております。




















コメント