スリムなブレスレット型のフィットネストラッカーで、スマートに健康管理。【EarBand (V08S/J】 ![]()
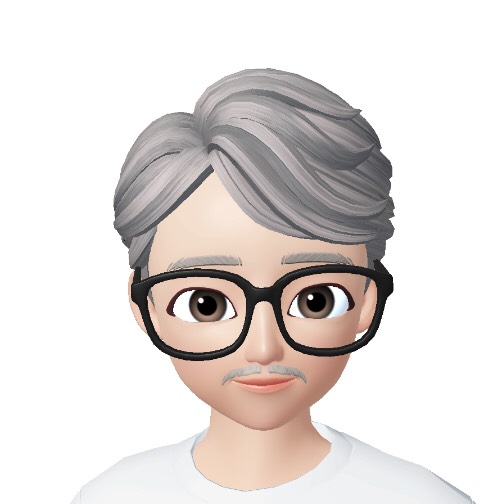
また、今までサッカーを数百試合見てケガの原因は指導者にもあるのではないかと感じたこともありました。そんなことも後半でお話していきます。
![]()
![]()
4年生、5年生と練習量や練習試合並びに大会が増加してきます。
3年生と比べ、身体への負荷が増加するとともに、ケガ人が増えた印象になりました
小学生年代でのケガ等の種類
オスグッド
整形外科学会系の情報をリンクしておきます。
http://www.jossm.or.jp/series/flie/s01.pdf
実は、私両足がオスグッドで、このツラさは良くわかるので、予防と早期治療を心掛けていました。しかし、長女と息子はなってしまいました。
オスグッドの治療で効果が見受けられた医院の紹介
息子が4年後半からオスグッドの痛みで、医院(接骨医院含む)に何件か通ったのですが
なかなか、納得できる効果が得られなっかったのですが、効果があった医院を紹介しておきます。(治療効果を保証するものではありませんので、ご了承ください。)
整体院 爽快さん(東京 千川)
自由診療なので治療費が高いのですが、特に医院長先生がお勧めです。
(弟子の方であれば、若干治療費が安い。)
治療は、無痛です。
これで痛みが、緩和されるの?
そんな感じになる治療です。
息子の場合、3回ほど通院し痛みがほとんど無くなりました。
また、知り合いでオスグッドで悩んでいた人にも、駄目もとで、ここに行ってみたらと紹介したところ痛みを緩和することが出来たと、連絡をいただいています。
オスグッドは痛みが緩和されてもスポーツを続ける上では、一緒に付き合って行かなくてはいけない性質のものですので再発防止や予防が大事です。
オスグッドの予防は、しっかりストレッチをして筋肉を和らげること
特に筋肉量の多い、太もも、背中の筋肉を柔らかくすることで、骨の成長速度に耐えうる
柔軟性を確保することだそうです。
予防には痛みが無くても、サポーターを付けることで痛みの発生を遅らすこと
と痛みの緩和が出来るようです。
娘がバドミントンで使っていたのは、こんなちっちゃいものです。
 | サポーター ひざ用オスグッド・シュラッタ―バンド 【ソルボDo 】【ひざ固定サポーター】【ひざ痛】 価格:3,190円 |
![]() 息子の場合
息子の場合
![]() 始めは、娘のサポーターを使用していたのですが
始めは、娘のサポーターを使用していたのですが
接触プレーでのズレ防止を兼ねて膝全体をカバーするタイプに変わりました。
 | ザムスト 膝 ヒザサポーター JK-1【ZAMST】野球 サッカー フットサル バレー ラクロス(JK-1)【smtb-k】【ky】*20 価格:3,344円 |
どちらでも効果は、あまり変わらないようですが
使用者が使いやすい方で、問題ないです。
息子は、比較的余計なものを装着するのを嫌がる性格なので
「これカッコいいなー」などと、仮面ライダーベルトを付けるような
よいしょをして、自ら付けることを忘れないように誘導してました。
それでも、紛失するので注意ください。
![]()
「腰椎分離症・分離すべり症
http://jossm.or.jp/series/flie/004.pdf
腰椎分離症は、小学高学年から発生するケースが多いようですね
息子は中1で経験することになってしまいました。
座ると腰が痛いので、授業を立って受けていました。
原因を特定することは難しいようです。
息子の場合、起点となりそうな試合をビデオ判定してみると、後ろから押された後から動きがおかしくなり、試合後から腰に軽い痛みが出て、数日して痛みが酷くなり、MRIを取ったところ腰椎分離症との診断
予防のための長友選手のトレーニング本を顧問の先生が貸してくれたことを覚えてます。
【AKA治療】療靱帯系や筋、軽度の肉離れの対応 運を天に任せた治療だったが!
ここでは、次女がバドミントンの県大会で途中棄権をした時の話なのですが
シングルスベスト8を決める準々決勝の試合中に動きに切れが無くなり、敗退
足を引きずるように私のところに目を赤くして来たのでした。
明らかに涙を我慢できない状態で涙が溢れてしまう状態・・・何事だ!
次女「次の順位戦に出て勝たないと県シードが取れない・・・」
私「右足か?」試合を見ていて踏み込みが出来ず、違和感は感じていた。
全く粘りが効かない、ま~相手も気づいていただろう。
次女「今は歩くのが精一杯」
私「まじ!」「出ても勝てる相手ではないだろ!」
次女「明日1回勝てばいい、ただクジ運次第・・・」
私「悪化する可能性が高いから棄権しな」「顧問の先生は?」
顧問の先生は、別会場に行っており、電話で「危険しろ」との命令が出た
私「早く治して、地区大会で優勝すれば問題ないだろう」
次女「うん・・・もう一つ近々にダブルスの大会がある、パートナーに迷惑かけたくない」
私「そんなこと言われても俺は、神様ではない!」
「ただ、こんなこともあるかもしれないと思って、調べておいた治療方法があるけど
試してみるか今より悪くなることは無いと思うのでチャレンジしてみるか?」
次女「怪しいの???」
私「分からないけど、痛みを緩和できるみたいだけど、理由が究明されていない」
そんなこんなで、運を天に任せてた早期回復を目論見
治療に向かうということで、病院に向かうことに
そこはちゃんとした整形外科で日曜日も営業している奇特な病院で
その治療資格を持っているのは医院長で、医院長の診察を受けれることを確認し
受付終了間際に滑り込みセーフ、車を降りたときには娘をオンブしていた。
治療方法はAKA治療というもので、
関節運動学的アプローチ、AKA(Arthrokinematic Approach)とは関節運動学に基づき、関節の遊び、関節面の滑り、回転、回旋などの関節包内運動の異常を治療する方法である。」
だそうです。
AKA治療については日本AKA医学会リンクを参照ください。
AKA治療をおこなった結果は、痛みがかなり解消された【不思議である】
医院長は、大腿骨を軽くマッサージしている感じ、施術が終わり
医院長が「歩いてごらん」「前屈して」「屈伸できる?」
歩くこともままならなかった娘が一番びっくりしているようで
「違和感と少し痛みがあるけど大丈夫!!!」
医院長曰く、
肉離れの痛みと身体の歪みから来る痛みは、結局のところ医学的には解明されていない
ただ、AKA治療は仙骨を調整することで痛みを緩和する効果は一部の医師の間で
研究が進められているが、治療方法として確立されていない。
そんな話でしたが、医院長はその研究者の一人だそうです。
医院を出た後の娘の感想は、「めちゃくちゃ不思議、もう歩ける」
そんな出来事がありました。
ですので、運を天に任せた治療方法としてAKA治療なるものがあることを頭の片隅に入れておかれてはいかがでしょうか。
※AKA治療はYouTubeでも紹介されていますが非常に高い治療費の請求する施術師が存在するようですので、注意してください。
『AKA治療』について動画をまとめてみた

(参考:AKA治療アカデミー出典)
骨折、打撲、捻挫(靱帯損傷)
・足関節後方インピンジメント症候群
・肉離れ
・半月板系の損傷
・脱臼
・骨折(手首、腕、足、疲労骨折)
など色んな種類があります。
4年生から6年生まで、チーム内に常時ケガ人がいたのですが、復帰まで半年くらいかかる子も何人かいました。
縦隔気腫(じゅうかくきしゅ) (呼吸器系)
過呼吸などは、呼吸器系で良く知られているものですが、
縦隔気腫(じゅうかくきしゅ)と言う疾患があります。
分かりづらいかと思いますが、二つURLをリンクしておきます。


素人の説明ですが、呼吸をしたとき口から肺に至るまでの経路の途中に穴が開き、体内に空気が漏れる
外部からの衝撃や、大声を出す、場合によっては咳などの力で、穴が開いてしまう。
とのことで、原因の特定は難しい。
どのスポーツでも起こりますが、あまり知られていないようです。
これにより、通常無菌状態を維持しているところに、菌やウィルスが入り込む状態が起きてしまう。
そこに菌が入り込むと、重篤な感染症に発展する可能性が高くなるそうで縦隔気腫になってしまったら、穴が塞がるまでじっと入院(軽いもので一週間程度)治療方法はそれだけです。
![]()
![]()
つぶやき(ケガ、ファール、重い怪我でも試合に出場させる。)
外傷による怪我は、ファールによるものがほとんどです。特に悪質なファールも指導者が謝れ、そんな一言で済ます。(お前が謝れ!)
・明らかに相手が怪我に至るプレー
・その試合で実力を発揮できなくするプレー
よくあるのが、接触プレーのように見せかけた ももかん、スパイクで削る。
明らかに、これらを故意に行っている子がいます。
これは、軽微ではなく重大な問題となるでしょう。
審判に、カードを貰わなければ良い、そんなことを考えている選手が多くいることは否めません。
どんな状況でも、スポーツマン精神を忘れず、プレーをする子を育てるべきです。
以前社会人のサッカーで、悪質なファールの訴訟があり、被害者が勝訴した事件があります。
一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターへリンク
サッカー協会は試合による障害について、訴訟を禁じているそうです。(え?)
小学年代もサッカー協会のルールの上で運営されていますが、故意によるものや、予め防げるものに関しては、このルールを無視する必要性がありますね。
(民法上でも故意や重過失については、証拠が揃えば、確実に損害賠償を成立させることが出来ます。)
故意による行為は、協会のルール以前の問題で、傷害罪にあたるということです。
最近プロなどでは、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー )が取り入れられていますが、小学生年代でも保護者がビデオを撮影したりしているので
大会主催者側は、試合終了後撮影されたビデオを証拠とし、苦情を申し立てることができるなど、工夫をすれば悪質なファールを減少させることに繋がります。
早々に何らかの対策を講じて欲しいものである。 ![]()
怪我を押しての試合出場!将来ある子供に悪質なファールを行ってでも勝ちにこだわる指導者
ファール防止には、各チームの指導者の徹底が必要。(予め危険なファールにならないように指導すべき方法)
強豪チームの中にも、いくつか試合中の指導で遅れたファールや危険なプレーをした子を即時、退場させているチームがありました。
息子の指導者もそうだったのですが、2年生くらいからファールに対し非常に厳しく指導として試合中に上手い下手関係なく、自チームの子供たちを何人も退場させていました。
すると、5年生、6年生ではファールが無くなり、チーム内にもファールは悪であることをチームメイト全員が認識し、プレーするようになる。
(ファールが全く無くなるというものではありませんが、しょうがないレベルや、今のファールに取られてしまうのか~?レベルのファールは、ありました。)
ですので、サッカーチームすべての指導者が、このように行うことで少年サッカー(学生年代全て)の怪我は半分以下に減ると私は考えます。
子供が悪質なファールをするのは指導者の責任に他ならない。
無能な指導者である。
結果として悪質なファールになるケースは、1対1で負けたときに起こりやすい。
単純に反応が早く、ポジション取りで相手が勝っていたことが多くの原因で
それを、特に悪質なファールで止める。
これは、既に勝負で負け、最悪の形で報復をするよなものである。
特に小学生に多く、中学世代でも中途半端な指導しかできない指導者のチームに多く見られる。
よくある最悪なケースは、試合中にマッチアップしている相手が自分より格上と判断し、相手を潰しにかかる方法に出る。
ヘディングで競ると見せかけて、膝で相手に思い切り「ももかん」を入れる。
または、足を踏む
ヘディングで競り合った後に、競り合で勝っていた方がモモを抱えて倒れこんだ場合には、結構な確率で故意の「モモかん」もしくは、足を踏む、可能性が高いので後でビデオで見てみると良く分かる。
最悪の場合には、笛も吹かれず競り合い後の相手の動きも封じることが出来ファールを宣告されなければ、悪の勝ちになってしまう。
これはヘディングでの一例だが、相手に打撃を与えられる状況は多岐に渡る。
試合中のこのようなケースは、カードが出ないことが多く、競り合った時の偶発的なものと見られることが多いようだ。
そもそも、このような行為を行う選手をフィールドに出してはいけない。
気づかない振りをしている指導者にも問題がある。
また、小学生の年代からVAR制を導入するべきである。
試合中が難しいのであれば、例えば試合後15分以内に保護者が撮影していたビデオを用い不服の申し立てが出来る制度を設けるなど、将来を含めた防止策として活用しても良いのではないかと思う次第です。
ファールによってサッカー活動が、困難になってしまった子も数人見ています。
そんな子が、1人でも減ることを願うばかりです。
おわりに
サッカーにおいては、コンタクトスポーツであることから、ケガは当たり前だ!
そのように、怪我を軽く考える指導者が多いように感じられます。
確かに軽度のケガ(打撲、軽い捻挫)などでは、重要な試合においては出場させることも
ある程度、理解できますが。
重度のケガ(靱帯損傷、腰椎分離症など)でも試合に出場させる、指導者の自制心の無さ。
子供が大丈夫、出たいと言った
過去にある子は、腕が骨折していてギブス状態で出場
あの子は、腰を痛めていたが出場した
など過去に発生した事象が判断基準を押し上げている。
小、中学生が自ら出した答えではなく、指導者はその後の結果にも責任を持って
試合に送り出すものである。
その子の先にある人生のことを含め、指導者の責任と私は思います。
最近はシッカリした指導者も多いので、悩む時には保護者、本人、指導者で
話合うことが大事である。(無理はいけない、無茶は更によくない)
プロの選手が故障で、登録抹消されるケースがありますが、
小学生だから大丈夫
中学生だから大丈夫。
そんなことを思う以前に、出場させないケガのレベルを認識していない。
特に、小学、中学年代で、将来を台無しにする可能性があるような怪我を負っている子を出場させる思考が理解できません。
娘がバドミントンを行っていたこともあり、サッカー指導者のケガに対する軽視は否めません。残念な限りです。
人として真剣に人生で最後の大会(高校や大学でしょうか)でない限り、
その途中(小学や中学)で挫折させるような子が出てきたとしたら、それは指導者の責任と考えるべきでしょうね。
また、小学年代では指導者がお前試合に出れるか?
と聞かれたときに、「出れませんと」言える子がどれほどいるか、疑問です。
ここは、保護者も子供の状況を充分に観察し、ハッキリと指導者へ進言することも大切です。![]()
小、中の年代での故障は子供自身と保護者も非常に悩むことになります。
特にチームでレギュラーであり、ゲームに出なければチームが負けてしまうような存在は無理をしがちになることも分かります。
そんな時に、一歩引いてサッカーで勝負すべき時はこの時期ではないと我慢(辛抱)することをお勧めします。
https://www.isojin.info/as-a-course-from-the-4th-grade-of-boy-soccer-elementary-school/



















コメント