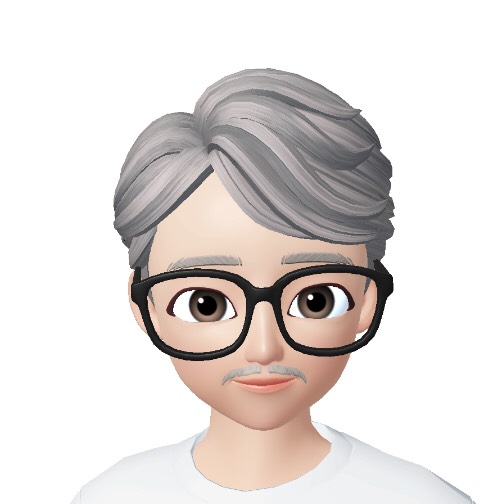
今回は、幼少期の続編になるのですが、入団した1年生~3年生の間で子供たちが指導によって変わっていった様子を分かりやすくするために、3年分書いてみることにしました。
また、3年生のところでトップチーム(レギュラー)の扱い方から、強豪チームの考え方にも触れていきます。(面倒だからまとめたわけではありません。)
少年団での年代別指導
・1年→根性
・2年→ポジション
・3年→フォーメーション 暫定トップチームの登場 強豪チームの考え方
指導者の評価項目はこんなもんで、チーム内のメンバーの中でそのすべての項目で一番になれば確実にレギュラにーなれる。
練習や試合での指導から感じた評価項目をお伝えしていきます。
チームによって評価の順位や指導する年代が違うと思いますので、所属チームの指導から判断してみてください。
それでは、息子が所属していたチームが徐々に変貌を!強豪なのか?
素人目線の振返りで、あの時は分からなかったが、あのトレーニングはここに生きてきているのか~。など指導者の方であれば当たり前のことかもしれません。
指導者の考えが保護者に伝わらない場合が多く、不平不満などでチームを去る
など、指導者の考えが伝わらない。または、理解できないなど
誤解が多く見受けられます。
指導者や保護者にも問題はあると思いますが、指導者の行動、指導内容について
いくつかのサッカーチームの指導方法に一定の法則とレギュラーの選定基準となる
項目(スキル)について、知ることが出来ると思います。
その項目からチームメンバーの順位を冷静に考えることが出来れば、お子さんの
順位も予想でき、全ての項目で1番になることを目指していけば、トップチームのメンバーになる可能性は高くなり、今、何を補うべきか目標設定のヒントになれば幸いです。
スリムなブレスレット型のフィットネストラッカーで、スマートに健康管理。【EarBand (V08S/J】 ![]()
少年団での年代別指導
さて、息子が入団することになっていたチームの練習が始まります。
前のブログでは、助っ人ととして参加していた程度ですが、チームメイトは35人
学年では多い方で、恵まれた年とのことです。
1学年上は20人。
1年生時の練習は数回、拝見しました。
練習時間
息子のチームでは、3つのグループに分けられている。
1,2年グループ (練習は週2と土日の大会やTM)
3,4年グループ(練習は週3と土日の大会やTM)
5,6年グループ(別グランドで週4と土日の大会やTM)
説明を受けに行ったときは、特に細かいところまで聞いていなかったので、改めて、チームに詳しい保護者(お兄ちゃんが入っている)から話を聞くことができた。 ![]()
![]()
練習メニュー
①多分、一般的ですがランニング、リフティング、パス練習などで体馴らし
②2対3や3対3による
切り返しやダブルタッチなどを交えたメニューで対人対応のメニューを色々と行っている。
③紅白戦人数が多いので、3チームや5チームに分けて対戦
ボールを2つ使った対戦もあり、敵味方同時にゴールするときもある。
④勝抜けダッシュ
⑤終わりのストレッチ
正味2時間ほどの練習
メニューをこなしていく中で、誰が一番足が速い、リフティングは誰が多くできたなど
サッカーに必要な要素で、一番出来ている子を褒めたり今日の優勝者は誰でした。
〇〇のプレーが良かった!などなど
みたいに、全員が目標を超える雰囲気で進めていく。
時には、前回はリフティングで●●君が何回で1番だったので、それを超えるように。
そして、今日はチャンスを2回あげるので
リフティングの数が多かった4人を次回の試合でスタメンで出す。と約束をする。
実際に約束を守るのです。
それを繰り返すと、4年生で普通のリフティングであれば1000回ほど出来る子が数名出てくる。
極力自然な形で競争心を煽り、同じチームでも全員がライバルであることをシッカリと認識させていく。
次に大きな成長は実践である。これは1年で目覚ましい成長を遂げる子が出てくる。
練習試合でのコーチング
小学生で始めて練習試合を観戦に
コーチの予想で均等な力量で分けられた3チームで公平に出場機会が与えられる。
キーパーもジャンケンで公平に。
そして、審判は前後半コーチが交代制で主審と線審を兼ねる。
ポジションはコーチの指示でとりあえず配置についた、試合が始まると団子状態が生まれる。(ボールも敵も味方も関係なく、ボールの近くを蹴る。)
野球での経験から非常に新鮮に思えたのが、審判である。
野球の審判は練習試合でも中立を保つため、指導者が審判になったとしても指示は出さない。
バドミントンなどもそうだ。
その反省などは、インターバルや試合が終わったあとである。
しかし、サッカーの場合、審判の役割を果していれば練習試合中に選手へのアドバイスがOKである。これは凄いことであり、コーチの器用さを痛感した。
コーチは試合を止めることなく、審判の役割を果しつつ、悪いプレーをした子を呼んで修正的な指導をするのである。
また、惜しいプレーをした子には、今のプレー以外にこんなプレーも出来る。
次は、同じ状況になった時に違うことも試せ。とプレーの幅を広げるアドバイスをする。
試合中に1人を呼んでアドバイスをすれば、1人欠けた状態となり、チームとしては不利であるが試合の結果などは関係ない。
今のお前を変えなければ、お前の成長はない。
なので、今やる。
そんな感じである。
これは、将来強いチームになるには、全員を成長させることが必須である。
(特に4年生までに、しっかりしたレギュラーメンバーを整える必要がる)
そんな考えだったのではないかと今では思えます。
1年生では、ドリブルで1人で頑張らせる。
1対1の場合に絶対負けないように、「負けるな~」と鼓舞する。
サッカーはコンタクトスポーツなので、身体のぶつかり合いの時も、
「頑張れ! こわがるな!」と鼓舞する。
ボールを奪われたときも、あきらめるなもう1回行け~
これは、いくつかのチームと対戦したが、指導者はやはり同じ指導をしているようだ。
(今から考えると、比較的強豪チームとTMを組んでいた印象です。)
1年生:実戦で必要なスキル(根性)
小学1年生の練習試合では実戦を想定し、将来必要なスキル(根性)の指導が徹底される。
・怖がらない(接触プレーや、相手が蹴るボールに対し逃げない意識を高める)
・1対1で負けない
・ボールを敵に当てない
・ボールを自分からラインを割らない
・バックパスをさせない
・FWへボールを出せ
・1人で抜いてゴールできるようチャレンジしろ
小学1年生ではこの7項目が徹底されていました。
また、赤字のところは、小学年代でレギュラーを確保する上で重要なポイントだったと思います。
1年次では練習試合で勝った印象が少ない。
大会でも、人数がいたので何試合か勝ちましたが、これで強くなるのか?
そんな1年間でした。
2年生実戦で必要なスキル(ポジション)とレギュラーの行方
2年生に入ると、団子サッカーからポジションを意識した指導へ変化していく。
また、2年生になると1年間の活動の中から暗黙の了解のように、暫定トップチームメンバーが決まってくる。
必要なスキルとしては
・相手より先にボールに触る
・テクニック(ドリブル、パスセンス、視野の広さ、意外性)
が加わり、1年生で必要なスキルとTMや大会での貢献度が加味される。
特に練習内容は変わらないので、TMや大会でのコーチングについて触れていきます。
2年生でもメンバーに色んなポジションを経験させ、ポジション毎に指示を出す。
FW:点を取る仕事。必ずゴールを狙う姿勢を徹底する。
味方がボールを奪ったときに、FWはどんなボールが来ようが、ゴールに結びつけるアクションを行わせる。
FWはオフサイドラインギリギリのポジションを保たせる。
試合中の指導者からFWに対する指示は、
「今のボールは狙えるだろ~」
この言葉が出たときに、え~あんなボールも狙わなくてはいけないのか~無理だろ
そんな、ことを心で思ったボールも多々ありましたが
また、「全く準備が出来ていない。」
「下がるな」
オフサイドを取られると「怠けている~、もっと早く戻れ~」
FWは大変だな~
負けると、一番怒られるんだよな~などと思っていました。
DF、MF:ボールを奪ったら、FWへボールを渡す。
→ 2年生の後半では、トラップやドリブルを工夫し、FWへ上手なパスをする子が徐々に増える。
MF:FWにボールが渡ったら、FWのサポート
団子サッカーにならないように、広い展開をさせて行く。(サイドチェンジ)
指示としては、敵が少ない方へボールを出せ!
こんな感じで、団子サッカーからの卒業に向けた指導が始まる。
特にFWは、チームで一番得点力があるやつがポジションに入ることを公言するのである。
2年生では、暫定FW候補が4人に絞られた。
2年生の練習試合や大会では少し、勝が増えたレベル。
既にパスサッカーやフォーメーションを取り入れているチームもあり、勝てない。
3年生実戦で必要なスキル(フォーメーション)とレギュラーの行方
3年生になり、姉妹チームから新戦力として3人が加入
暫定トップチームメンバーの誕生
1,2年と比較的公平に、メンバーの育成を行い、暫定トップチームメンバー(13人)が決まった。
このメンバーには、いくら上手くても練習の出席率が悪い子は入らない。
トップチームに入れる基準は1、2年生からのスキル上位の子が選ばれている。
比較的公平な順位付けが行われている。
・相手より先にボールを触る(常に先、インターセプト率が上がる)
・テクニック(ドリブル、パスセンス、視野の広さ、意外性)
・怖がらない(接触プレーや、相手が蹴るボールに対し逃げない意識を高める)
例えば、
相手の子がボールを思い切り蹴るふりをして、相手がよけるアクションを取ったとき
にドリブルで横をすり抜けていく、そんなフェイントプレーに引っかからないようにする。
・1対1で負けない
(ボールを持った時に、テクニックで抜く、適切なパスで有利な展開に持っていく)
・ボールを敵に当てない
・転ばない (追加)
・ボールを自分からラインを割らない
・FWへボールを出せ
当初の指導項目からウェイトが落ちたもの。(ポジションによりますが)
・バックパスをさせない 注 苦し紛れのバックパスは怒られる。
・1人で抜いてゴールできるようチャレンジしろ
この基準は、身体的な差もやはり影響してきます。
有利になるのが、身体が大きいこと
早熟で、足も速いなど。
ただ、身体が大きくなっていなくても、テクニックで補っている子が多く見受けられました。
結構難しいのかなと思ったところは、怖がらない。
敵にボールを当てない。
この部分なのでしょうか。
試合になると頭の中が真白になってしまったり、指導者から怒られたことで
委縮してしまう。
怒られても、怒られた理由だけ理解し、受け流せる精神力が必要であったり
試合の緊張を逆に楽しみ。頭の中が真白にならないメンタルが必要ですね。
(大きい大会になるとDFのプレッシャーは大きいと、予想します。
まして、決勝などになれば、失点はDFとキーパーの責任のウェイトが高い)
各項目は点であり、点が線となって行く。
トップチームの試練、試合の取組が大きく変わりました。
トップチームの試練!
何が試練かと言うとチームの目標は、全員試合に出ること、勝つこと
ほとんどの試合で、まず、初めに登場するのはトップチームで、最悪でも前半で試合を決めることを指示されます。
その目安は、3点差。
3点差となれば、トップチームの補欠を前半中に投入して、後半は全員交代となります。
このサイクルが上手く機能すればトップチームに上がろうとする子(Bチーム)も、出場機会が与えられ、アピールするチャンスが生まれます。
また、これにより更なる競争が生まれる。
またこの仕組みには、トップチームが格下相手と戦う時間を少なく出来る利点があり、緊張感の無い試合や気の緩みに繋がる試合からトップチームを早々に離脱させる意味がある
息子は、こんな考え方のチームに属していると、俯瞰しながら判断しました。
こうなると、トップチームの役割は非常に大きく、トップチームが強くなければ円滑にチーム運営を行うことは難しい状態になります。
要するに、トップチームが弱ければ、他の子の出場機会やアピールチャンスが減り、不公平感が生まれるのです。
素人おやじなりに、指導者の行為にはどんな意味があるのか、息子がトップチームに入るには、何をすればよいのかを知るためにチームを分析した内容です。
私も当時は、渦中の栗のような位置にいたり、保護者の不平不満なども見聞きしました。
そんな中、俯瞰した位置で全体を見ると、こんな考えに至ったわけです。
チームにより、指導方法、運営方法は違うと思いますが、これを読んだことで
今一度考えてみよう。
チームのTMや練習を見に行き、子供のレベル、指導者の指導方法を再確認される方が増えると幸いです。
(素人でも、ポイントを少しずつ理解していけば、お子さんに的確なサポートができるます。)
サッカーチームのレベルなどで、差は出てくると思いますが、強豪チームでレギュラーになるには、結構な苦労が必要です。
3年で追加された練習
チーム固有のフォーメーションから
・セットプレー
・パスワークの精度UP
指導は徐々に厳しくなってきた雰囲気。
子供たちの辛さを紛らわすように、遠征の帰りにガリガリ君で好感度ポイントを上げる指導者。
首の皮一枚でトップチームに残った息子
3年でのチーム成績
J下部も出場する
アントラーズカップ出場、決勝トーナメントへ
GPフェスティバル 神奈川 決勝トーナメントへ
三島山田杯 1位リーグへ
野田教育リーグ 決勝トーナメントへ
など
小学1年でのグダグダチームが少しづつ形を見せ始めた時期でした。
このころから、故障する子も増え始めました。
![]()
![]()
![]()
![]()
参考までに:トップチームの運営
・トップチームは、別枠で大会に参加することがある。
別枠で参加する大会は、参加する子だけに連絡がいきます。
チーム内では、他の子との公平性を保つための仕組みで別勘定を採用している。
参加に必要な交通費、大会参加費、食事代など
指導者が1人当たりの参加費を連絡し集合時に渡す。
ま~当り前と言えば当り前ですね ![]()
![]()
スクールでのトレーニング ← 参考程度にお伝えします。
強豪チームのレギュラーになるには、やはり色々なテクニックを教えてくれるサッカースクールは欠かすことが出来ません。
スクールでは、実戦で使える又は、実戦で必要なテクニックを教えてもらえました。
自分は、息子ではないので、細かいことは分かりませんが。
チームで教わるテクニックよりも、多かったそうです。
息子にスクールで教わったことが試合で有効だったテクニックは何か聞いてみたところ。
チームでも教えてもらったことと、重複することが多かったけど、一番は、ボールを受けたときに、ボールを見ないでドリブルやパスをすることと言ってました。
ただ、クレーグランド(土のグランド)だと予想に反した動きをボールがするので、使えないときがあるけど、非常に便利と言ってました。
チームでも教えてもらったものを、さらに精度を高めることが出来たそうです。
上を目指すうえで、どうぞサッカースクールもご検討ください。 ![]()
![]()
![]()


付録 評価項目の理由が今一つ分からない方へ
説明が結構難しいのですが、これらの項目は点であり、プレーをする場合に別の項目とリンクして線になる性質があることを理解ください。
・相手より先にボールを触る(常に先、インターセプト率が上がる)
常に相手より早くボールを触ることで、試合を有利な状態で進めることが出来る。
足だけを出すのではなく、相手とボールの間に身体を入れることで、相手に触らせない状態を作れれば最高(味方の攻撃態勢に入れる)。
強豪チームと普通チームが対戦した時によく見られる光景で、強豪は常時プレッシャーを仕掛けてくるので、普通のチームはペナルティーエリア内に入ることも出来ずに試合が終わってしまう。
相手より、先に触るには、練習試合でも常に意識していなければ、身に付きません。
・テクニック(ドリブル、パスセンス、視野の広さ、意外性)
5,6年生の強豪チームの試合を見ていると、寄せが速いのでドリブルをする時間が試合中非常に短い。ボールを4タッチ出来ればいい方です。
特にペナルティーエリア付近では、トラップミスをした瞬間に、ボールを失う。
ドリブルで抜けるのは、キーパーと1対1になった時くらいです。
但し、ペナルティーエリアに入ると、足を引っかけるとファールになったりするのでドリブラーは、そのエリアが見せ場かもしれません。(ただ、最低でも2タッチで打たなければ身体を入れられてしまいます。)
・怖がらない(競り合いなど)
単なるヘディングでも怖がる子がいるので、別項目にしました。
・1対1で負けない
(ボールを持った時に、テクニックで抜く、適切なパスで有利な展開に持っていく)
・ボールを敵に当てない
ボールを敵に当てると、カウンターのようになって失点につながることもあります。
シッカリ敵をかわして、パスをする技術と視野の広さが必要です。
・転ばない (追加)
3年生頃から転ばない指示が、追加。
相手に足を掛けられて転ぶシーンはよくあると思うのですが、転ばないことを徹底すると不思議なもので、結構な確率で避けられるようになっていくものです。
危険察知能力も上がるように思えます。
少し古いですが、中田英寿選手は転ばないことで有名です。
・ボールを自分からラインを割らない
失点に繋がりそうな場合に、ハッキリとクリアー(外へ出す)時を除いて
ラインを割ってはいけない。
上記のケース以外でボールを出すことは、味方の攻撃を潰すだけ。
サイドポジションも味方からのパスでラインを割らないよう全力で走り、マイボールをキープすること。
・FWへボールを出せ
これは、サッカーでは当たり前なのかもしれませんがボールを持った時、常にトップを見ろ。
それが強豪高校ではよく言われています。
まず、FWにボールを預けられれば、チャンスが拡がるからなのですが自分の責任を逃れるように、近くの子にパスを出しておしまい。
そんなプレーが、見受けられたら修正しなくてはいけません。
自分がボールを持っていなければ責任は無い。
そんな考えのプレーはチームを劣勢にしてしまう可能性が高い。
傾向として逃げのバックパスを多く使う子は、試合の始めは良いが頻繁に使うと
頭のいいFWの子は、その癖を見抜きインターセプトを常に狙っているので、この癖は直さなければいけない。
癖を直すには、技術を磨くとともにバックパスをさせない状況でプレーをさせる。
これば早いうちに直しておいた方が良いと思います。
上の年代である11人制ではよく目にしますが、チームの攻撃態勢を整え、もう一度やり直す時に使うのが本来あるべきのバックパスで、苦し紛れのバックパスは最悪の選択と考えるのが良いと思います。
長くなりましたが、付録を含め今回はここまでです。
どうもありがとうございました。






















コメント